育児休業手当金
短期給付
| 本頁に関連する届書・請求書用紙 | 申請書 | 記入例 |
|---|---|---|
| 育児休業手当金請求書 |  |
 |
| 育児休業手当金変更請求書 |  |
 |
| 育児休業手当金延長請求書 |  |
 |
| 育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書 |  |
 |
組合員(任意継続組合員を除く。)が、育児のために休業したときに子が1歳に達する日(子の1歳の誕生日の前日)までの期間について支給します。(※)
また、次の支給要件のA又はBに該当する場合は、子が1歳に達する日の翌日(子の1歳の誕生日)から最長で2歳に達する日まで(子が1歳6か月に達した時点で再度申請が必要)の期間についても支給します。
子の範囲については、法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託されている子等が対象となります。
請求回数については、産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に2回まで請求できます。子の出生後8週以上の期間については育児休業手当金を男女それぞれ2回まで請求できます。
- 雇用保険法の規定による育児休業給付金を受け取ることが出来る場合は、当共済組合からは支給できません。
雇用保険法の規定上、支給を受けることができず、当共済組合に請求する場合は、支給されれない旨が確認できる書類を添付してください。
パパ・ママ育休プラス
育児休業手当金の支給期間が1年を超えない範囲で(出産日及び出産後の休業期間を含む)、育児休業の対象となる子が1歳2か月に達する日まで支給期間が延長されます。
適用条件は、「配偶者が育児休業に係る子の1歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業を取得していること」です。ここでいう育児休業は、あくまでも育児介護休業法又は地方公務員の育児休業等の関する法律に基づく育児休業等に限定されており、各自治体が独自で定める育児目的の休業や、労働基準法第65条に定める産後休暇等は含まれません。
また、パパ・ママ育休プラス制度で更に支給期間を延長する場合は、当該育児休業に係る子がパパ・ママ育休プラス制度育児休業手当金の支給期間の末日後の期間について、支給期間延長の要件①又は②に該当するか否かの判断を行います。要件に該当した場合は、2歳に達する日まで(子が1歳6か月に達した時点で再度申請が必要)の期間についても支給します。
支給要件
- 育児休業に係る子について、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所もしくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳※に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
ただし、次の①~③すべての条件を満たす者となります。
また、当該条件を満たすことを確認するため、以下の書類の提出が必要となります。- 育児休業手当金支給対象期間延長
事由認定申告書(給14-1)(以下「申告書」という。) - 市区町村に提出した保育所等の利用申込書の写し(以下「利用申込書」という。)
- 市区町村より発行された保育所等における保育が当面行われないことが明らかとなる通知(以下「入所保留通知書等」という。)
- パパ・ママ育休プラス適用者が延長請求をする場合はパパ・ママ育休プラス終了日(最長1歳2か月)となり、再延長の請求をする場合には1歳6か月に達する日となります。
-
育児休業の申し出に係る子が1歳に達する日までに保育所等への入所申込みをしていること。
ただし、1歳に達する日までに入所申込みを行おうとしたものの、「一定の理由」により申込ができなかった場合は、申告書の理由欄及び医師の診断書、障害者手帳の写し等により確認が必要となります。
「一定の理由」とは、育児休業の申し出に係る子の疾病や障害により特別に配慮が必要であり、市区町村から保育体制が整備されていない等の理由により、申込みの受付ができないとされた場合が該当し、市区町村への相談なく組合員の判断のみによって申込みを行わなかった場合はこれに該当しません。
なお、「一定の理由」に該当する場合は、下記②及び③の確認は要しません。 -
①の申込みの内容が、速やかな職場復帰を図るために保育所における保育等を希望しているものであると認められるものとして、次のア~ウのいずれも満たすものであること。
- 利用(入所)開始希望日を育児休業の申し出に係る子が1歳誕生日以前であること。
なお、添付する入所保留通知書等については、交付年月日が子の1歳誕生日の2か月前(4月入所の場合は3か月前)の日以降であることが必要です。
ただし、交付年月日が当該日より前の日付の入所保留通知書等しかなく、入所保留中は市区町村から新たな入所保留通知書等が発行されない場合は、申告書の理由欄に子の1歳誕生日において保育が実施されないことを記載の上、直近の入所保留通知書等を添付してください。 - 市区町村に対して、入所保留扱いとなることや育児休業を延長することを積極的に希望する旨の意思表示を行っていないこと。
- 利用(入所)希望の保育所等が、合理的な理由なく通所に片道30分以上要する保育所等のみとなっていないこと。
具体的には、申告書に記載された「利用(入所)申込みを行った保育所等の中で、自宅又は勤務先から最も近隣の施設名と通所時間(片道)」が30分未満となっていることが必要です。この際、通所時間は通所する場合に利用する予定の交通手段による自宅からの片道の所要時間によることとし、送迎サービス等を利用する場合は送迎場所までの片道の所要時間とします。
また、通所時間が30分以上となっている場合は、申告書によって合理的な理由に該当することが必要です。合理的な理由とは、以下の場合です。- 利用(入所)希望の保育所等が以下のいずれかを満たす場合
- 組合員又はその配偶者の通勤の途中で利用できる場所にある場合
- 勤務先(配偶者の勤務先含む。)からの片道の通所時間が30分未満の場所にある場合
- 自宅から30分未満で通所できる保育所等が無い場合
- 自宅から30分未満で通所できる保育所等では、職場復帰後の勤務時間・勤務日に対応できない場合
- 子の疾病や障害により特別に配慮が必要であり、自宅から30分未満で通所できる保育所等が無い場合
- 兄弟姉妹と同じ保育所等の利用(入所)を希望する場合
- 自宅から30分未満で通所できる保育所等が、いずれも過去3年以内に、児童への虐待等について都道府県又は市区町村から行政指導等を受けていた場合
なお、申告書に上記dからfの理由に該当する旨の記載がされている場合は、これに該当することが確認できる書類の添付が必要です。
(添付書類の具体例)- 医師の診断書や障害者手帳の写し等(上記dの場合)
- 兄弟姉妹の在籍証明書等(上記eの場合)
- 当該保育所等が行政指導等を受けた事実に関する市区町村の公表資料、保育所等の公表資料(上記fの場合)
- 利用(入所)希望の保育所等が以下のいずれかを満たす場合
- 利用(入所)開始希望日を育児休業の申し出に係る子が1歳誕生日以前であること。
- 子の1歳誕生日の時点で保育が実施されないこと。
ただし、これまでにやむを得ない理由なく保育の利用を辞退した場合を除く。
具体的には、申告書又は入所保留通知書等の備考欄などで保育所等の内定を辞退していないこと。辞退している場合は、申告書の理由欄によって「やむを得ない」理由に該当する旨の記載が必要です。「やむを得ない」理由とは、申込みを行ったときから内定を辞退したときまでの間に住所や勤務場所等の変更その他これらに準ずる事情の変更があり、内定した保育所等に子を入所させることが困難となった場合が該当します。
- 子が1歳6か月に達する日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められる場合においては、①~③を準用します。
例えば、子が1歳6か月に達する日後の期間について、子が1歳誕生日において保育所等に入所できず支給期間の延長を行っており、引き続き入所できない状況が続いている場合も、再度の支給期間の延長に際しては、原則1歳6か月に達する日後の期間について、保育所等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、保育の実施が行われない旨の新たな確認書類の提出が必要です。
ただし、市区町村から新たな証明書等が発行されない場合(入所保留通知書等の保留有効期限が到来していない、1歳誕生日に係る申込時以降新たな申込みの機会がなかった等)は、組合員からの申告書等による確認を行います。
- 育児休業手当金支給対象期間延長
-
常態として育児休業に係る子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であった者が、右のいずれかに該当した場合
(組合委が当初から1歳を超える期間について育児休業を取得している場合は除く)- 死亡したとき
- 死負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業に係る子を養育することが困難な状態になったとき
- 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなったとき
- 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週を経過しないとき間
- 組合員が別の子に係る産前産後休業又は育児休業・別の家族に係る介護休業を開始したことにより子の育児休業を終了した場合で、新たな休業が対象の子又は家族の死亡等により終了した場合に、1歳に達した日後の期間について育児休業手当金が支給されます。
支給期間
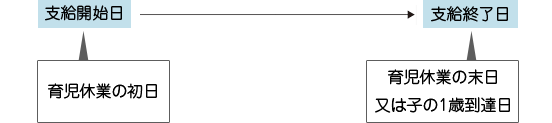
- 上記の支給要件に該当した場合、支給終了日は子の1歳6か月・2歳到達日又は支給要件に該当しなくなった日の前日のいずれか早い日になります。
支給額
支給期間1日につき180日(土曜日及び日曜日含む)に達するまでは標準報酬の日額の100分の67に相当する金額を、それ以降は標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給します。
ただし、標準報酬の日額が給付上限相当額を超える場合は、1日につき給付上限相当額を支給します。
- 給付上限相当額」とは、雇用保険法第17条第4項第2号ハで定める額(同法第18条の規定により変更された場合には変更後の額)に相当する額を基に計算した額です。(毎年8月に変更されます。令和6年8月時点 給付割合67%は14,334円、50%は10,697円))
支給方法
請求書の提出があった場合、請求初日から提出のあった月の標準報酬の日数に給料日額の100分の67相当を乗じた額を、翌月に支給します。
以後、毎月、180日(土曜日及び日曜日含む)に達するまでは100分の67を、それ以降は100分の50を、標準報酬の日数を基に計算した額を翌月に支給します。
- 支給期間中の土曜日及び日曜日は、給付日数から除きます。
(給付日数から除くのは土曜日及び日曜日に限られるため、祝日法による休日や12月29日から翌年1月3日が平日にあたる場合、その日は給付日数に含みます。)
手続き
| 区分 | 提出書類 | 添付書類 |
|---|---|---|
| 育児休業を開始したとき | 育児休業手当金請求書 | 育児休業承認請求書(写)、又は、育児休業願(写)又は辞令(写) |
| 育児休業中である者が、支給要件の①又は②に該当したとき | 育児休業手当金延長請求書 | 育児休業承認請求書(写)、又は、育児休業願(写)又は辞令(写)、養育状況変更届(写)など(すでに添付済の場合は不要)
支給要件を証明する書類〔保育所の保育が実施されないとき〕
〔配偶者の死亡のとき又は婚姻を解消したとき〕
〔配偶者の負傷・傷病のとき〕
〔配偶者の出産のとき〕
|
| 子の1歳の誕生日の翌日以後に育児休業を取得又は再取得した者が、その時点で支給要件の①又は②に該当したとき | ||
| 育児休業期間を変更(延長・短縮)したとき | 育児休業手当金変更申請書 | 育児休業承認請求書(写)、又は育児休業願(写)、又は辞令(写)、養育状況変更届(写)など変更後の期間のわかる書類 |
| 支給要件の①又は②に該当しなくなったとき | ||
| パパ・ママ育休プラスを開始したとき | 育児休業手当金請求書 | 組合員の配偶者が当該育児休業に係る子の1歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業をしていることが確認できる書類(写) |
